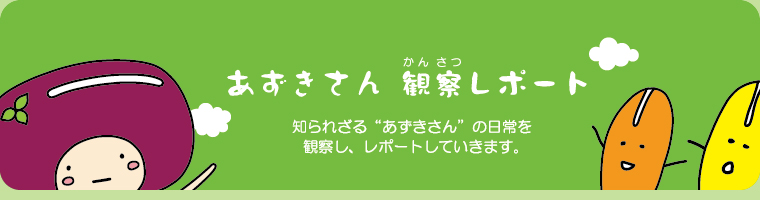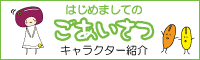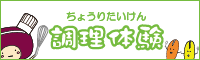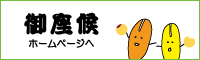おしらせ
もうすっかり季節は春ですね。
お庭の木々も青々と茂り、
お隣の工場ショップのお店も見えなくなりました:deciduous_tree:
今年に入り味噌を仕込んでいます。
味噌で使われている豆は一般的には大豆ですが、
それ以外にも黒豆を使った味噌、
珍しいものでは落花生や青えんどうでも作ることができます。
今回は小豆を使った味噌を仕込んでみました。
小豆で豆腐はできないとしても、味噌はできるはず!:sparkles:
材料はシンプルで、小豆と米麹と塩のみです。
米麹は近所の麹屋さんへ買いに行きました。
紙袋に入れてもらった麹はほのかに温かく呼吸をしているようで
食べ物ですが生き物を扱う心持ちになりました。:relieved:
自家製の味噌は暖かくなる前頃に仕込み、
季節が進み気温が高くなるにつれ麹の発酵が進みます。
徐々に熟成していき、夏を越え秋から冬にかけて食べごろを迎えます。
初めての味噌作りなので、知人に聞いたり、本を参考にしての試みでした。
正直どうなるのかは分かりませんが、
味わえる日を目指し見守っていきたいです。

もし、小豆で味噌を作ったことがある方がいらっしゃいましたら、
情報をお待ちしております。:smiley:
味噌作り初心者のまめ丸でした。
2023年4月19日 10:28 AM |
カテゴリー:おしらせ |
コメント(0)
みなさん こんにちは~!
3月3日は甘酒を飲む どうも~みつまめです(´ω`*)🍒
 おひなさまかざりました🌼
おひなさまかざりました🌼
あずきミュージアムにひな人形を飾りました:sparkles:
可愛いです~:heart:
 五人囃子の笛・太鼓~♪
五人囃子の笛・太鼓~♪
藤豆さんにはちゃんと「この五人囃子には太鼓を持たせて~」と
教えてもらっていましたが
今年からいません…さみしい…
帽子も取れるし小道具も笛や太鼓…左右上下誰が誰やら…:sweat_drops:
でも頑張りました:fire:
頑張って並べた雛飾りはなんだか格別です!
 かわいいな~と思いながら飾りました
かわいいな~と思いながら飾りました
『ひな祭りの風習の起源は平安時代にまでさかのぼるといわれています。
平安時代、自分の厄災を代わりに引き受けさせた紙人形を
川に流していたそうです。
 こちらが「流し雛」です
こちらが「流し雛」です
それがやがて豪華なひな人形を飾るようになり、祝うようになりました。』
(出典:旧暦で楽しむ日本の四季 二十四節気と七十二候より)
子どもの幸せを願う思いは今も昔も同じですね:star2:
どうか健やかに幸せに・・・:sparkles:
2023年2月23日 10:37 AM |
カテゴリー:おしらせ |
コメント(0)
お久しぶりです。藤豆です。
最近ますます寒くなってまいりましたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか?
あずきミュージアムではお正月の準備が始まりました。
12月16日(金)~18日(日)には「餅花作り体験」を開催しました。
 あずき茶で染めた餅花は、やさしい桃色が特徴
あずき茶で染めた餅花は、やさしい桃色が特徴ミュージアム館内ではこのような花器に餅花を生けていますが、
ご家庭でも飾りやすいような方法を考えてみました。
柳の枝を丸くし、洋服をかけるフックやクリスマスリースを
かけていた場所に飾るアレンジ方法です。
「かける場所がない」「そもそもリースは飾らない」といった場合は、
このような和風のトレイに飾ってみてはいかがでしょうか?
餅花は柳の枝に丸い餅をつけ、稲穂に見立ててその豊作を祈る飾り。
小豆の豊作を願って、小豆の莢を添えてみました。
下の白い紙は茶席などで使用されるお懐紙を使用しています。
お懐紙を使用しなくても、白い紙を一枚添えるだけで
パッと華やかな印象になります。
小豆の莢のかわりに飾り用の稲穂を添えたり、
干支や縁起物の置物を添えてもいいかもしれません。
こちらは玄関のシューズボックスの上やチェストの上に置いて
鑑賞していただけます。
当館では毎年1枚目の写真のように壁に取り付けた花器に生けていますが、
飾り方に正解はありません。
(ミュージアムの庭園に生えている万両を利用してアレンジしましたが、
南天の実や小さな松、冬の花等を添えても華やかになると思います)
様々なアレンジ方法を試して、自分だけの餅花を飾ってみてくださいね!
2022年12月24日 5:25 PM |
カテゴリー:おしらせ |
コメント(0)
« 古い記事
新しい記事 »