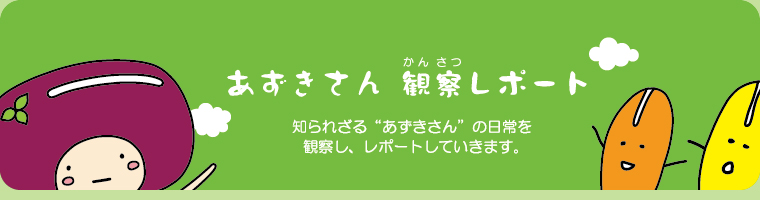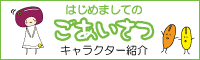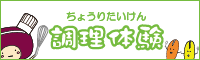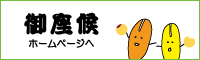ガイドツアーQandA
またまた更新をSABOっていました:sunglasses:
前回の雪とミュージアムから一転
ここ数日はやっと暖かくなってきて
庭園の木々が小さな花をつけていたり
鮮やかな緑の葉っぱを見ることができたりと
散歩しているとたくさんの春を感じることができました:sunny:
さて、来週末に実施する
【特別企画】小豆博士のガイドツアー:memo:
2014年3月29・30・31日(土・日・月)
①11:20~ ②13:30~ (1時間程度)
※あずきさんがガイドするわけではありません。
ガイドツアーって… :speech_balloon:
展示を順に解説してくれるの:question:
むずかしくないかな:question:
小豆の栽培について重点的に知りたい:exclamation:
どんな先生なのかな:question:
などなど、様々なギモンがあると思います。
今回はそんなギモンに答えていきます。
Q.どんな先生なのかな?:thought_balloon:
A.今月来ていただける先生は 沢田 壮兵 先生
帯広畜産大学名誉教授で農学博士の先生です。
楽しく明るく、参加者に合った内容で
小豆についてやさしく教えて頂けます。
いつも帯広からお越し頂いていますが
前回は、電車で北陸の遺跡などを巡りながら
一人、ゆっくりと旅をしながら帰られたそうな。。。
Q.展示を順に解説してくれるの?:thought_balloon:
A.ガイドツアーに決まったスケジュールありません。
参加者のご希望やお好み、質問に合わせ
先生が案内してくれます。
質問が質問を呼び、奥ぶか~い話になることもあれば
ミュージアム全体をガイドされることもあります:sparkles:
Q.むずかしくないかな?:thought_balloon:
A.参加者によって先生が合わせてガイドしてくれます。
わからないことがあったらどんどん質問してください:sparkles:
Q.小豆の栽培について重点的に知りたい:thought_balloon:
A.重点的に一か所を学びたいときは
ガイドスタッフか先生にお申し付け下さい。
参加者が複数の場合はご希望に添えない場合もありますので
午前中や平日のガイドツアーがねらい目ですよ:sparkles:
さて、質問に答えていくうちに
先生のハードルを上げているような気がしてきました:sweat_drops:
とにかく、このガイドツアーは
「先生が話をして、参加者がそれを聞くだけ」
というものではなく
「先生と会話をしながら、楽しい学びの一日を過ごす」
そんな感じです。
暖かい木漏れ日に春を感じる庭園を散歩したり:herb:
ゆっくりした館内で楽しく小豆を学んでみてはいかがでしょうか:memo:
来週末は先生とガイドスタッフでお待ちしています。
さて先日、
あずきさん先生(仮)に『あずきの栄養』をガイドしてもらっていたら…

「ん?」
何かに気付いた様子のあずきさん。
どうやら『美容に役立つ』という内容に改めて興味を持ったみたい。
小豆に含まれるビタミンB2とB6が、美容に良いようです。
『ごぼうの3倍もある食物繊維』にも興味を持って
結局、私そっちのけで展示に見入ってしまいました。
勉強中のあずきさん。先生への道はまだ遠い…。